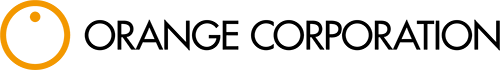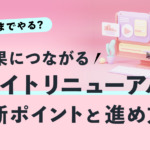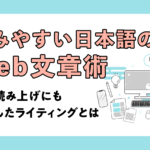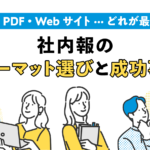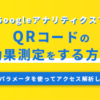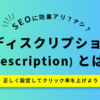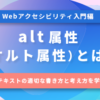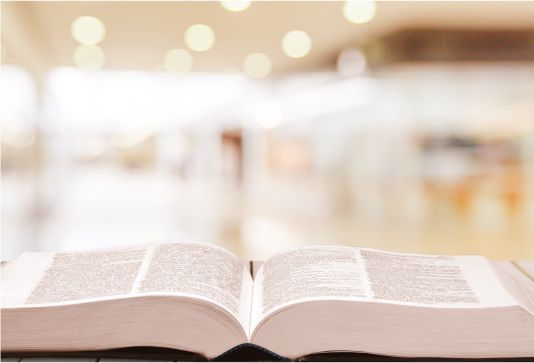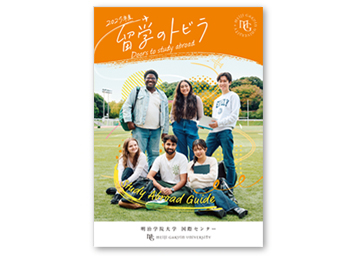ブログ
Blog
- POSTED :
読みやすい日本語のWeb文章術|音声読み上げにも配慮したライティングとは
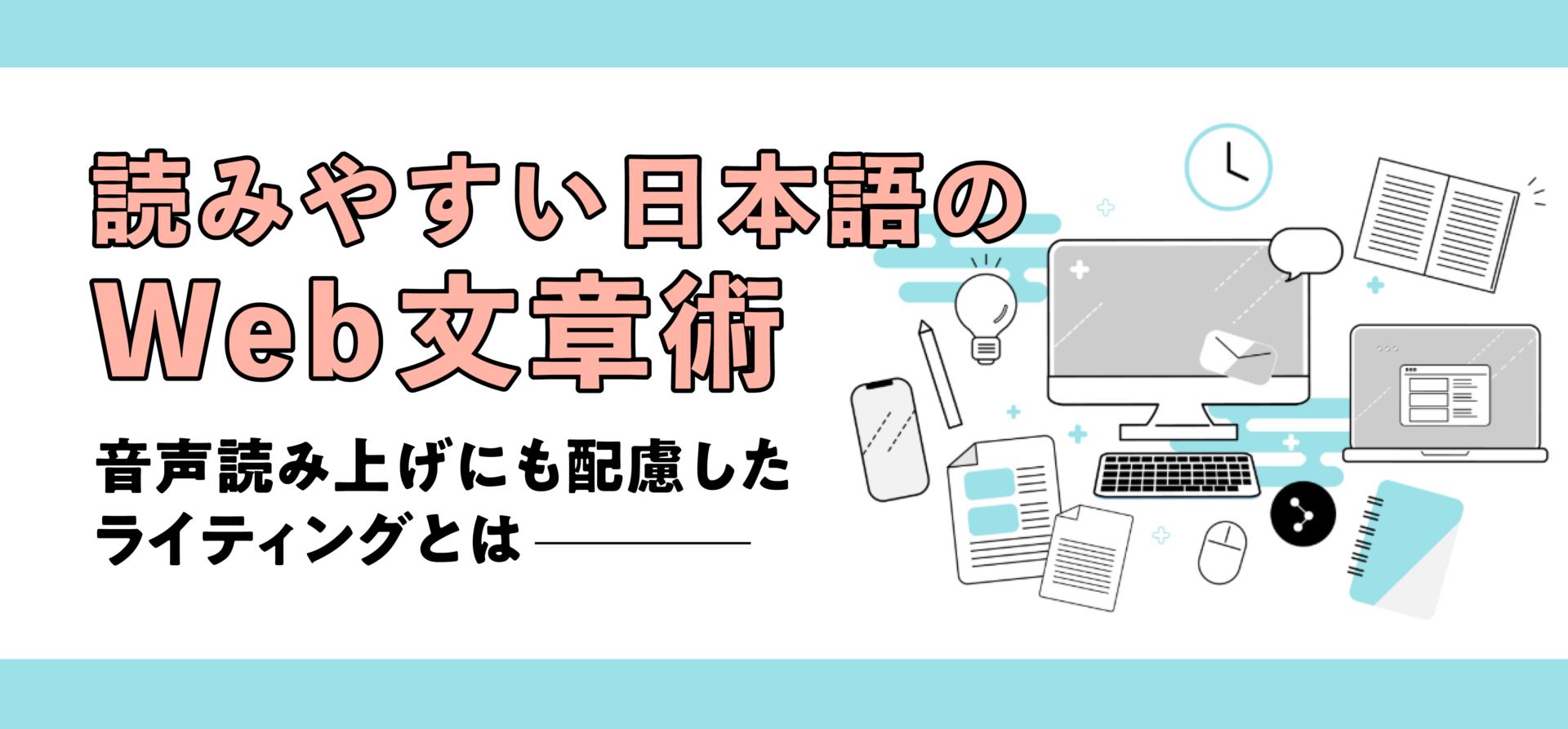
はじめに
「分かりやすく書いたはずなのに、なぜか伝わらない」——そんな悩みを感じたことはありませんか?
サステナビリティサイトの立ち上げや刷新を検討する中で、情報の“伝え方”に不安を抱く広報・CSRご担当者の声をよく耳にします。
特に、ステークホルダーの多様化が進む今、高齢者や外国語話者、視覚に不安のある方にも配慮した「誰にでも読みやすい」「聞いても理解しやすい」Web文章が求められています。
本記事では、Webライティングの基本原則に加え、音声読み上げといったアクセシビリティ観点に配慮した実践的な文章術をご紹介。
企業の発信力を高める、やさしく伝わるコンテンツづくりの第一歩にぜひお役立てください。
Webアクセシビリティ・「音声読み上げ機能」とは?
Webアクセシビリティとは「高齢者や障害者を含めて、誰もがホームページ等で提供される情報や機能を支障なく利用できること」の状態や程度のことをいいます。
中でも「音声読み上げ機能」は、視覚障害者や読み書きに困難を感じるユーザーにとって、ウェブコンテンツにアクセスするための重要な手段です。また、スクリーンリーダーと呼ばれるソフトウェアを使用して、ウェブページ上のテキスト情報を音声で読み上げることで、情報を得ることができます。
【関連記事】:「評価されるサステナビリティサイト制作に重要なWebアクセシビリティ対応3選」(https://www.orange-sha.co.jp/blog/web09_sus-a/)
音声読み上げ機能を最大限に活用するためには、ポイントをおさえたうえでコンテンツを作成する必要があります。
「明確に伝える」Web文章の3つの基本原則
普段話す口語と、文字を読む文章では、書き方が少し異なります。特に、情報を伝えるためのWeb文章において「読みやすい」と感じてもらえるものは、多くの場合、3つのポイントを押さえて書かれていることが原則となります。
1. 一文一義で、文を短く切る
× NG例
現在、私たちのチームでは、新サービスの立ち上げに向けて、社内外の関係者と調整を重ねながら、仕様の確定やデザインの詰めを行っており、来月中のリリースに向けて準備を進めています。
○ 良い例
現在、私たちのチームでは新サービスの立ち上げを計画しています。社内外の関係者と調整しながら、仕様やデザインを詰めています。来月中のリリースを目指して、準備を進めているところです。
Web文章では、「一文が長すぎる」ことが大きなハードルになります。特にスマホでは、長い文が画面に収まりきらず、読みづらくなる傾向があります。
音声読み上げでも、長すぎる一文は聞き手にとって負担になります。
このため、目安として、一文は60文字以内とし、接続詞や修飾語はできるだけシンプルにすることを意識すると読みやすくなります。
また、句読点を適度に使い、意味の切れ目を明示することも大切です。
2. 主語と述語の関係を明確に
× NG例
提案内容を確認した後、修正点をまとめて共有しておいたが、確認が遅れたので全体への展開は保留にして、後日説明することになった。
○ 良い例
担当者の■■は、提案内容を確認後、修正点をまとめて●●部署に提出した。しかし、●●部署での確認が遅れたため、社内全体への展開を保留にした。後日、■■から●●部署へ、修正点について直接説明する予定です。
日本語では主語を省略することがよくありますが、音声読み上げではこれが混乱のもとになりがちです。
聞き手が「誰が・何が」行動しているのかを、理解しやすくするためには、主語はなるべく省略しないようにしましょう。
また、倒置や長い修飾語の挿入を避け、主語と述語の距離を近く保つことも効果的です。
単文で構成すると、文法構造も明確になります。
3. 読点(、)を活用して意味の切れ目を明示
× NG例
本日、午後の会議で、担当者が、資料の修正について、追加で、説明を、行う予定です。
本日午後の会議で担当者が資料の修正について追加で説明を行う予定です。
○ 良い例
本日午後の会議で、担当者が資料の修正について、追加で説明を行う予定です。
読点は「読みやすさ」「聞き取りやすさ」の両面で重要です。
読み上げでも、読点は一瞬の間として認識され、文章の意味や流れを整理する助けになります。
ちなみに、一般的には読点の間は0.1秒から0.3秒程度に調整されることが多いです。
読点の打ちすぎは、かえってテンポを乱すこともあるため、書き手が意図的に、意味の区切りとして必要な時に使うことが大切です。
「音声読み上げ機能」に配慮したWeb文章のポイント
次に、「音声読み上げ機能」のソフトからも音声発信のため、配慮すべきポイントをお伝えしましょう。
1. 曖昧な指示語は避ける
× NG例
当社は、新しい教育支援サービスを開始しました。これにより、学習の進捗管理が簡単になります。さらに、これを使えば、保護者との情報共有もスムーズに行えます。
○ 良い例
当社は、新しい教育支援サービスを開始しました。この教育支援サービスでは、学習の進捗管理を簡単に行えます。また、このサービスを利用することで、保護者との情報共有もスムーズに進みます。
「これ」「その」「あちら」などの指示語は、画面上では前後関係から意味が分かっても、音声で聞くと何のことか分からない場合が多くあります。
特に新しい段落やセクションでは、文脈をリセットする意識を持ち、指示語の代わりに「このサービス」など具体的な語句を使うと分かりやすくなります。
2. 正しい文脈での漢字の読み上げを意識する
× NG例
校了後に重複の確認を行ってください。
○ 良い例
校了(こうりょう)後に、重複(ちょうふく)の確認を行ってください。
漢字の読み間違いも文章の理解を妨げます。読み間違いが起こりやすい難読漢字や、専門用語にはふりがなや補足説明を加えましょう。
「生」などの一般的な漢字でも、「なま」と読むか、「せい」と読むかで伝わり方が異なります。
また、「重複」は「ちょうふく」と読ませるか「じゅうふく」と読ませるか、読み上げソフトによっても読み方は異なるため、文脈で判断できる書き方を意識することも大切です。
3. 半角カタカナ・記号・英語の表記に注意
× NG例
A社&B社の共同プロジェクト詳細は、営業部→開発部に連携してください。CMS導入済みです。
○ 良い例
A社とB社の共同プロジェクト詳細は、営業部から開発部に連携してください。
また、CMS(コンテンツ管理システム)はすでに導入済みです。
Webライティングでは「&」「@」「→」などの記号を使う場面もありますが、これらは音声読み上げでは意図しない読み方をされることがあるため、注意が必要です。
また、誤読やエラーのもとになるため、半角カタカナは使わないようにしましょう。
略語も目で見たらイメージできるものが、音声で聞くと分からなくなってしまうものもあるので、正式名称を補足するようにしましょう。
見出し・段落・リストで「読みやすい構造」をつくる
「音声読み上げ機能」での観点を含め、Webアクセシビリティに大きく関わる点が、文章全体の構築・構成です。
1. 小見出し(H2・H3)で内容を整理
見出しがあることで、視覚的にも、音声的にも構造が伝わりやすくなります。特に音声読み上げソフトは、見出しを認識して読み上げるため、情報の取捨選択がしやすくなります。ソフトの認識を高めるためにも、「まとめ」「ポイント」など、セクションの要点が分かる見出しにしたり、具体性のある見出しにしたりするなどの工夫をしましょう。
2. 段落を短く、1ブロック3〜4行を目安に
段落が長すぎると、読む側は途中で息切れしてしまいます。特にスマホでは段落が1画面に収まらないとストレスに感じることもあります。3〜4行ごとに段落を分けたり、改行によって文章に「余白」をつくったりするなど、見やすくするための工夫をしましょう。
3. 箇条書きを活用して情報を整理
箇条書きは情報をスッキリと整理でき、視覚的にも音声的にも分かりやすくなります。また、各項目の末尾に「。」を付けることで、読み上げ時に区切りが明確になります。項目数は3〜5個がベストでしょう。長すぎるリストはかえって読みにくくなってしまいます。
企業サイト・Webメディアにおけるライティング改善のメリット
誰にでも伝わる言葉は、多様なユーザーに届くことになります。多様なユーザーが「読みやすい」と感じられることで、ページ滞在時間や回遊率の向上が見込まれ、UX・SEOの改善にもつながるでしょう。
また、アクセシビリティ対応は、企業の社会的責任の一環でもあり、これに対応することで信頼性向上にも直結します。読みやすい文章は、コンテンツの価値そのものを高める要素であると言えるでしょう。
まとめ|伝わる文章は「書き手の思いやり」から生まれる
「明確に伝える」Web文章の3つの基本原則
1. 一文一義で、文を短く切る
2. 主語と述語の関係を明確に
3. 読点(、)を活用して意味の切れ目を明示
「音声読み上げ機能」に配慮したWeb文章のポイント
1. 曖昧な指示語は避ける
2. 正しい文脈での漢字の読み上げを意識する
3. 半角カタカナ・記号・英語の表記に注意
見出し・段落・リストで「読みやすい構造」をつくる
1. 小見出し(H2・H3)で内容を整理
2. 段落を短く、1ブロック3〜4行を目安に
3. 箇条書きを活用して情報を整理
読みやすく、聞きやすく、分かりやすい文章は、特別なスキルと言うよりは、「誰のために、何を、どう伝えたいか」という思いやりの姿勢から生まれます。
読者の状況を想像し、表現を見直すことで、文章は伝わりやすいものに変わっていきます。
ちょっとした工夫の積み重ねが、Webサイトの信頼感やユーザー体験を大きく変えることになるでしょう。
「読みやすい・伝わるWeb文章」で、貴社のサステナビリティをもっと届けませんか?
アクセシビリティや多言語対応を考慮したサイト設計について、お気軽にご相談ください。
オレンジ社では紙・PDF・WEBの形式に対応した制作を承っています。特に、現地市場に合わせた柔軟な対応力が強みです。ご予算や社内体制に応じて、最適な企画・制作フォーマットをご提案します。
ご依頼方法やお問い合わせ
株式会社オレンジ社では、クライアントのニーズに応じたカスタマイズプランを提供し、予算に合わせた一気通貫の制作を実現します。制作プロセスはヒアリングから始まり、要件定義、デザイン・開発、公開後の運用サポートまで一貫して対応します。納期や費用についてのご相談も随時承っています。
制作の無料相談実施中
現在、株式会社オレンジ社では、無料で制作に関する相談を実施中です。資料のクオリティ向上や、より効果的な情報発信を検討されている企業の皆様は、ぜひ一度ご相談ください。専門スタッフが貴社のニーズに最適なソリューションを提案いたします。
CATEGORY
NEW POST
RANKING